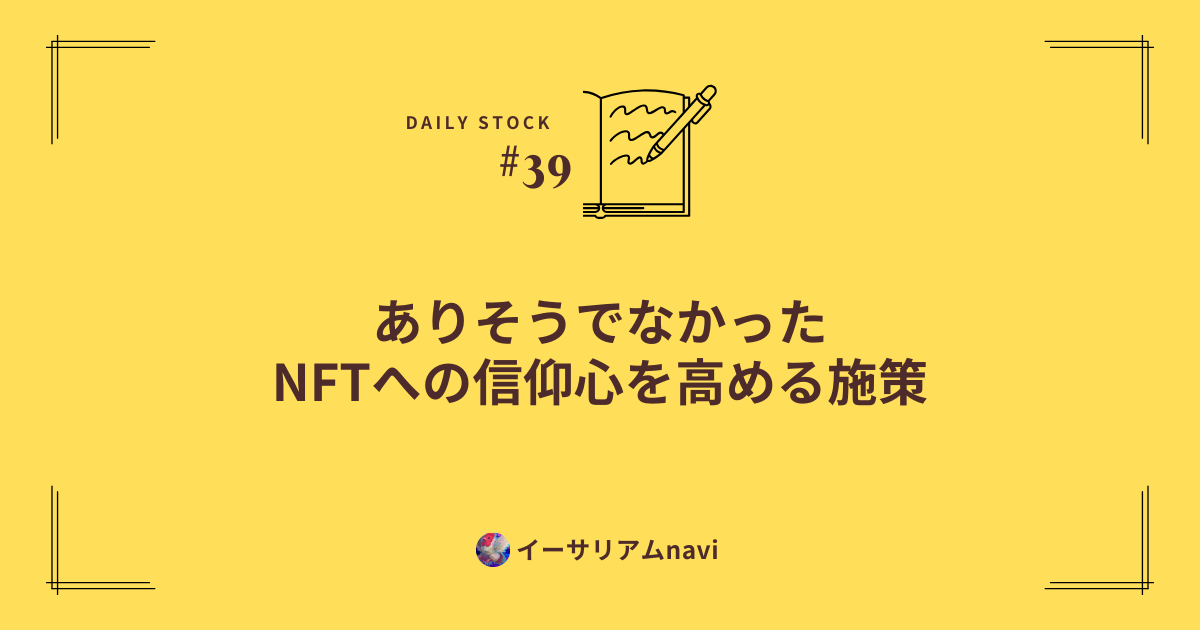どうも、でりおてんちょーです。
今日のDaily Stockは、ありそうでなかったNFTへの信仰心を高める施策についての話です。
今日のDaily Stockは、ありそうでなかったNFTへの信仰心を高める施策についての話です!
— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) August 1, 2024
NFTプロジェクトに不足しているのは、経済的インセンティブよりも信仰心だと個人的には考えているため、このような施策は非常に筋が良いのではないかと感じている。https://t.co/rGUXzcLfph pic.twitter.com/rUzkRdXQJu
この続き: 2,354文字 / 画像3枚
先日、miinさんがSNPITというSnap to Earnのプロジェクトについて取り上げていて、その取り組みが興味深いと思ったので、今回はこちらを題材にしたいと思う。
SNPIT、HISモデルのカメラNFTを発売
— miin l NFT情報コレクター⚡ (@NftPinuts) July 30, 2024
⚡️写真を撮りトークンを稼ぐGame Fi
⚡️イベント等で全国各地での写真撮影による旅行機会の創出、観光資源の発掘に寄与
⚡️401個 (全10種)/350MATIC相当 / 9月末発売予定
ルーレットででた都道府県での撮影でパラメータ上昇する機能も📷️https://t.co/6fo6YPR1A6 pic.twitter.com/8upjOZViVx
SNPITについては詳しくないが、少し調べたところ、まず最初にカメラNFTを購入し、専用アプリをスマホにインストールすることで写真撮影が可能になるとのこと。
また、ユーザーは撮影した写真を予測市場のような形で投票にかけて勝負することができる。そして、そこで獲得したトークンを使ってカメラNFTをレベルアップさせることで、撮影する画像の画質を向上させることも可能らしい。
そんなSNPITが今回、全国各地の写真撮影イベント用にカメラNFTをHISとのコラボで販売したというのが、先ほどmiinさんが取り上げていたニュースの大まかな概要である。

トークンモデルやNFTの売り方は一旦置いておいて、この試作で個人的に興味深いと感じたのは、リアルな要素を巧みにコンセプトに組み込んでいる点だ。
というのも、NFTプロジェクトに不足しているのは、経済的インセンティブよりも信仰心だと個人的には考えているため、このような施策は非常に筋が良いのではないかと感じている。
NFTを使った施策では、デジタル空間との相性の良さから、メタバースやDiscordなどのコミュニティでユーザーエンゲージメントを高めるものが目立つ印象である。
しかし、私たちはリアルな世界に生きる人間であり、ホルダーの熱量を高めたいのであれば、リアル空間での施策を行った方がその効果は高いと考えられる。
実際、コロナ後にリアルイベントが爆発的に増え、Zoomよりもリアルで会うことの価値に多くの人々が気づいたであろう。
これらの要因から、NFTを使った施策でもリアル要素があった方がホルダーの熱量は高まると考えられる訳だが、今回のSNPITの取り組みは、これまでのNFTプロジェクトには見られなかった「NFTホルダーの聖地」を現実世界に創出する試みであり、その点で非常に興味深い。

例えば、宗教やアニメには信者を集めるための聖地が存在する。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が集まるエルサレムや、仏教には四大聖地がある。
また、SLAM DUNKの聖地である鎌倉高校前駅や、となりのトトロの聖地である狭山丘陵など、コアファンが多いアニメには、聖地がある。現実世界の聖地が用意されることで、ユーザーは写真を撮ったり、人との繋がりを深めたりすることができ、IPに対する信仰心を高めることに繋がる。
山古志のNishikigoi NFTもこの取り組みに近いのかもしれないが、こうした聖地巡礼の概念をNFTプロジェクトを通じて創出する可能性があると、今回のSNPITとHISのコラボレーションを見て感じた。
— Atsu 社会彫刻 (@AtsushiHayashi) July 29, 2024
ちなみに、このような聖地を設ける施策は、日本人とも相性が良いのではないかと個人的に思っている。
以前、SoulbondsというSBTプロジェクトを紹介した際の考察パートで言及したが、日本人は仏教に入信してから仏像を拝むのではなく、仏教の教理を唱える前に「美しい仏像というモノそのもの」を崇拝し、そこから間接的に宗教心に目覚めていくという説がある。
欧米とアジアは「聞く」文化と「見る」文化の違いとも言われる。この違いは実はエンタメ業界にも深く根ざしており、その市場規模や産業構造の成り立ちにまで影響している。(中略)仏教の仏像も、本来はイスラム教のように「形あるものを作って拝むこと」自体が邪道と言われ、中国でも量産されていなかった時代に、日本人は仏像をバンバン彫って普及させ、ガンガン拝んだ。仏教の教理を唱えるより前に、美しい仏像というモノそのものを崇拝し、そこから間接的に宗教心に目覚めていく。(中略)「聞く」文化の欧米とは対極的であり、かつ「見る」文化のアジアにおいても「手を動かして作る」文化をオリジナルで築き上げた日本は、まさに職人大国として長い歴史をもつ。そして宗教をある意味「使いながら」、自分たちの芸術的素養を耽美し、出来上がった偶像物を信仰することを良しとしてきた。
出典元:中山 淳雄 『推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』(日経BP、2021年)250ページ

要するに、NFTの仕組みや原理を理解してからNFTを購入・使用するのではなく、先にリアルな聖地を巡礼し、間接的にNFTの仕組みや原理をホルダーに理解させるアプローチの方が、相性が良く裾野も広がるのではないかと思う。

その意味で、今回「SNPIT」が提唱したカメラNFTを活用した新たな旅のあり方は、今までありそうで無かった「NFTホルダーの聖地」を現実世界に創出する試みだと感じた。
宗教やアニメがそうであるように、聖地ができることで聖地巡礼という概念が生まれ、ホルダーのNFTプロジェクトに対する信仰心も間接的に高まりやすいのではないだろうか。
こうした少し変わった切り口から、今後の「SNPIT」とそのコミュニティの動向をウォッチしていきたいと考えている。