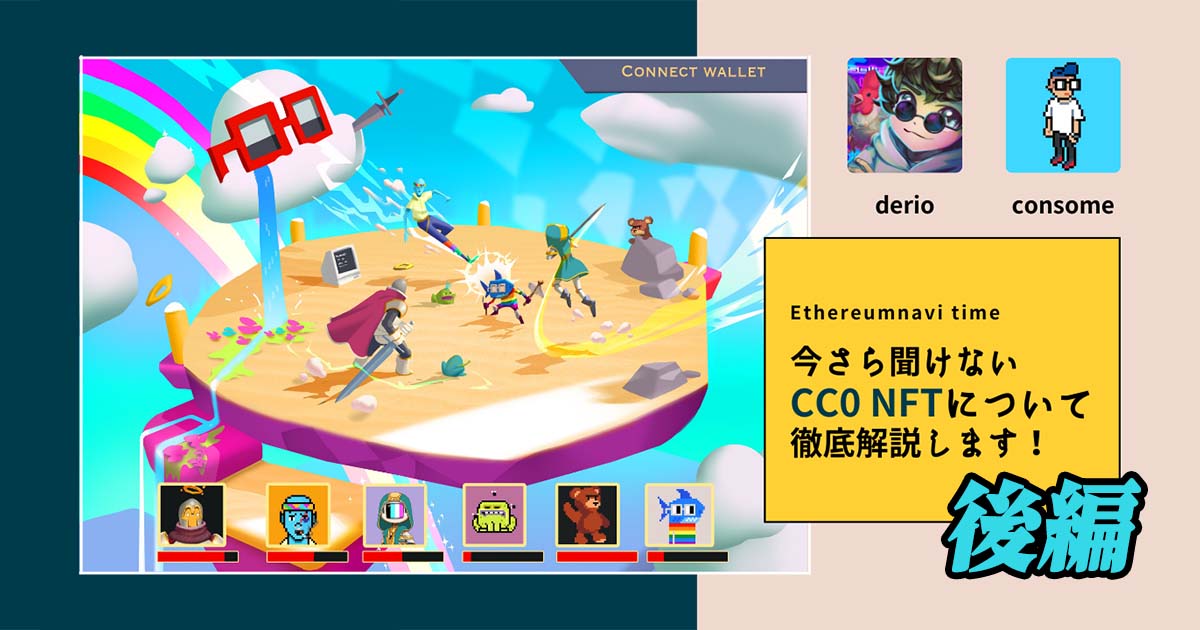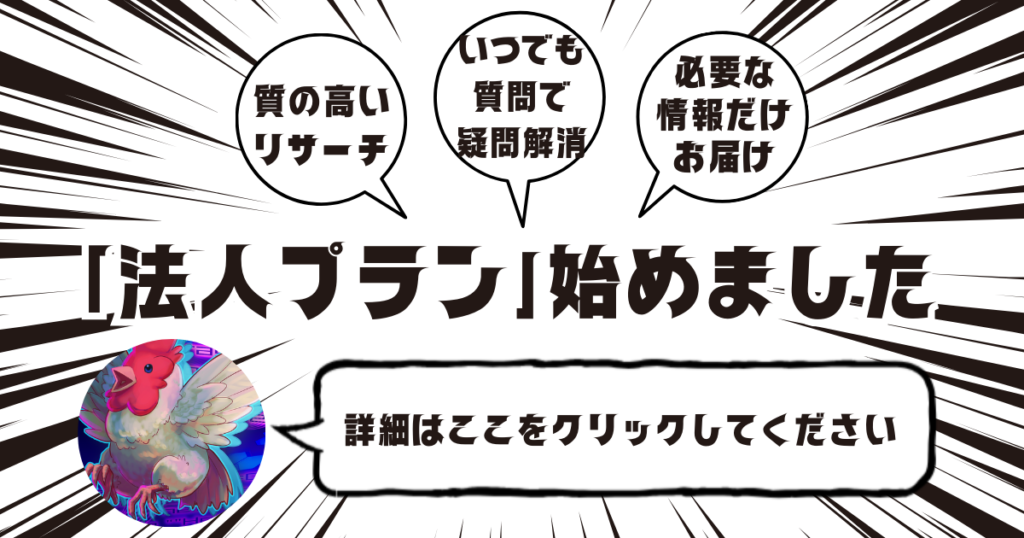今回は、先日のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」(※追記:諸事情により現在は非公開)について文字起こしをおこない、記事コンテンツとしてまとめていきたいと思います。
本記事は『後編パート』となります。『前編パート』に関しては以前別の記事でまとめているので、まだご覧になっていないという方はこちらを先に一読されることを推奨いたします。

では、この記事の構成について説明します。
まずは、前編で述べた『NFTをCC0ライセンスにするのは何故?』を踏まえて、どのようなNFTプロジェクトがCC0化に向いているのかについて、私見を交えて解説してまいります。
次に、NFTにCC0ライセンスを採用することのデメリットについて解説いたします。
最後に、『CC0 NFTのデメリット』項で述べた課題を解決するための一案として、「NounsDAO」のモデルと施策などについて私見を交えて解説してまいります。
本記事が、CC0 NFTが内包する特徴やデメリット、CC0 NFTのデメリットを解決するための一案とその実例などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。
イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。
CC0 NFTに向いているプロジェクトの特徴

 derio
derioでは前回までの内容を踏まえて、どんなNFTプロジェクトにすればCC0ライセンスが活かせるのか、またそもそもどういったNFTプロジェクトがCC0を採用することに向いているのか、これらのテーマについて私がいろんなCC0 NFTプロジェクトを見てきた上で感じた特徴について、いくつかピックアップしてご紹介したいと思います。
この続き: 13,213文字 / 画像22枚
まとめ



というところで時間も良い感じになってきたので、一旦これで終わりということで最後に締めさせてください。





おめでとうございます!
僕もいろんな海外のメディア見ていますけど、イーサリアムnaviほどコアなプロジェクトがまとまっているものは、世界を見渡しても他にないです。
これ本当です。ポジショントークじゃないです。



consomeさんにそんなこと言われると…困ります(照)



こんなにコアに刺さるメディアは見たことないので、ぜひ続けていただいて。
結構いろんな人に知っていただけるようになりましたよね?



いや〜、ありがとうございます!
そうですね、方向性としてはあんまり流行っているコンテンツとかを取り扱うことが少ないメディアなのでPV数とかが伸びにくかったりしたんですけど、1年やっていると徐々に知ってくださる方が増えてきて良い感じになってきているので、2年目も頑張っていきたいと思います。



ぜひぜひ、応援しています!



ありがとうございます!


今回は、先日のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」について文字起こしをおこない、【後編】の記事コンテンツとしてまとめてまいりました。
本記事が、CC0 NFTが内包する特徴やデメリット、CC0 NFTのデメリットを解決するための一案とその実例などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。
また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。
🆕記事をアップしました🆕
— イーサリアムnavi (@ethereumnavi) September 9, 2022
以前のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」についてまとめました✍️
本稿は【後編】であり、以下についての記事です。
💡CC0 NFTに向いているプロジェクトの特徴
💡CC0 NFTのデメリット
💡NounsDAOの事例をご紹介https://t.co/z1taDRcc84
本記事内では文字数の関係上、配信した内容の全ての部分をお伝えすることはできておりません。
また励みになりますので、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。


イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。
- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/
- Twitter:@STILL_Corp
- メールアドレス:info@still-llc.com