どうも、でりおてんちょーです。
今日のDaily Stockは、NFTにおけるイケア効果とエッグ理論についての話です。
今日のDaily Stockは、NFTにおけるイケア効果とエッグ理論についての話です!
— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) July 17, 2024
クリプトのオーナーシップの概念は、法的な所有権とは異なるインターネットネイティブな性質があるため、単にトークンを配布するだけではなく、ユーザーが所有者と感じられる設計が必要がある。https://t.co/IQMco1i5p8 pic.twitter.com/HWhdUOXvY0
ゲームもいきなり戦わせるのではなく、箱庭のように一手間かけたりした方が良いというFBしたばかりだったので共感。
— LIB🧑🍳🌏 (@libdefi_jp) July 17, 2024
NFTにおけるイケア効果とエッグ理論|Daily Stock #31 https://t.co/6GyIbMaQ7i #イーサリアムnavi via @ethereumnavi
NFTを投機商品として見た場合はいらない要素だろうし、ENSで考えると色々捗るけど、、、
— 貫く剣 | 🪞➕🧬♦️ZEEK🎩 (@piercesword) July 17, 2024
既存のものを考慮するとアバター感レベルまでいかないと厳しい印象https://t.co/vKh884XyFp
エッグ理論とは、、、と深掘りしてたら沼った∈(・ω・)∋
カゴでも死後でも無い方
この続き: 1,734文字 / 画像4枚
昨今、NFTを作成することが容易になった時代において、NFTを保有するユーザーのエンゲージメントを高めるためには、単なる利用価値や金銭的な価値以上のものが求められるようになりつつある。
NFTを販売したとしても、保有しているだけでコミュニティや投票などの活動に参加・関与してくれなければ、プロジェクトを次のステージへと進めることは難しいと言える。こうした課題を解決するために役に立ちそうなのが、「イケア効果」と「エッグ理論」なのではないかと最近思っている。
以前Daily StockでNFT2.0「保有→消費」について書いたが、これと少し似たような話なのかもしれない。つまり、いかにユーザーに「持っている感」を抱かせることができるかが重要になると思っている。

「イケア効果」とは、自分自身で作り上げたものに対してより高い価値を感じる心理的メカニズムを指す。
これは、スウェーデンの家具メーカー・イケアが提供する組み立て家具の事例から名前を取っている。
要するに、顧客が自分で家具を組み立てることで、その家具に対する愛着や価値が高まるという心理的現象なのだが、NFTにおいてもこの効果を活用することができるのかもしれない。

例えば、ユーザーが自分自身でNFTミント時のカスタマイズや設定を行うことで、そのNFTに対する愛着が湧き、結果的に高い満足感を得ることができる。
これは単なる便利な機能や金銭的な価値以上に、ユーザーにとって特別な体験を提供し、そのNFTに対する価値を高める効果があると考えられるのかもしれない。
一般的にコレクタブルNFTの一次販売では、NFTの特性(traits)に対してレアリティ要素を設け、自分がどの特性を有したNFTを購入したのか分からないようにランダム性を持たせて販売されることが多い。
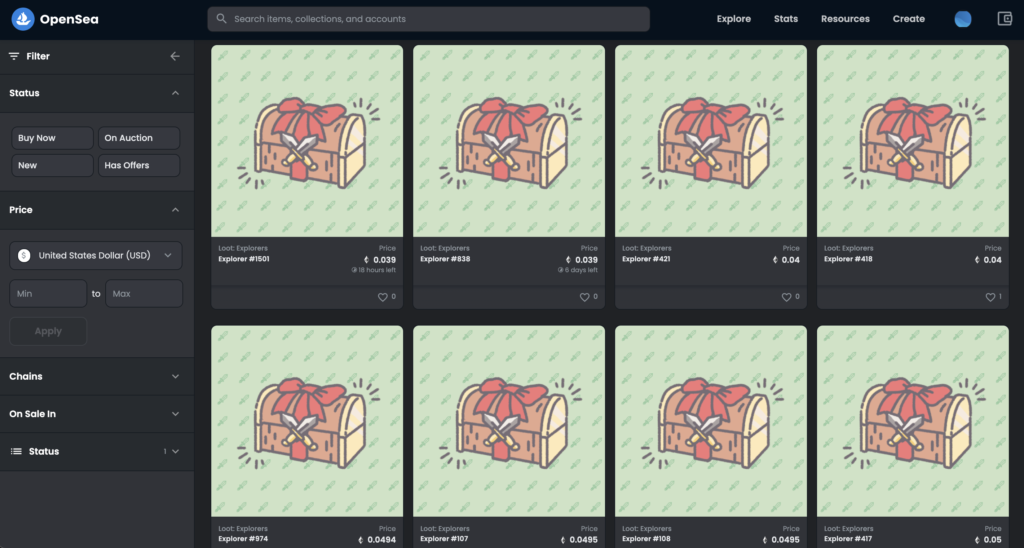
この手法では、ユーザーの期待感を煽ることができ、また良いレアリティのNFTを獲得できれば高値で再販できる確率も高まるため、経済的なインセンティブにより完売まで持っていけるケースが多いことも確かだろう。
ただ、その後のユーザーエンゲージメントを高めるフェーズで挫折してしまうケースが多いことも、ここ数年の実証実験を見てきて明らかになったと個人的には思っている。
こうした課題を解決するために、例えばHyperLootなどはミント時に自分で特性をカスタムできるようにしたり、Blitmapでも自分で合成できるようにしたり、Homageでも自分が好きなNFTをリミックスするというイケア効果メカニズムを採用していたのではないかと思っている。

また、イケア効果と似た概念として「エッグ理論」というものも存在する。
エッグ理論は、インスタントケーキミックスの販売不振から生まれた概念である。
初期のケーキミックスは、あまりに簡単すぎて消費者に罪悪感を抱かせ、売れ行きが悪かった。そこで、製品に卵を追加する工程を導入したところ、消費者は自分がケーキ作りに貢献していると感じ、売り上げが飛躍的に伸びたというものだ。
この例は、ユーザーが自分で何かを作り出すことが、製品に対する心理的所有感を強めることを示していると言えるだろう。

何でも自動化できる便利な時代の中で、いかにユーザーの一手間というエッセンスを加えることができるかが、NFTを保有するユーザーのエンゲージメントを高めるために必要になりつつある。
クリプトの世界におけるオーナーシップの概念は、法的な所有権とは異なる「インターネットネイティブ」な性質を持っている。そのため、単にトークンを配布するだけではなく、ユーザーが所有者として感じられるように設計する必要がある。
それによって、NFTやコミュニティに対する忠誠心や貢献度が高まり、心理的所有感と実際の資産所有権を組み合わせながら、より持続可能なエコシステムを構築するための一歩になるのかもしれない。

